|
35 鎌倉古道 柏原 地蔵畑 醒井 地蔵堂 八坂神社 番場 蓮華寺 摺針峠 鳥居本 彦根
滋賀
26 km 2003/03/30
西行・一休など 鎌倉街道へ
24 滋賀 醒井、番場、磨針、小野
2003/03/30
西行・一休など 能舞台の名所・旧跡へ
|
  JR柏原駅から歩く。柏原の成菩提院は、お寺では少ないらしい、節分の行事があるが、中山道を少し西に行った所のお寺さんでも、節分をやっていると聞いて尋ねてみた。どのお寺か判らなかった。勝専寺、教誓寺 をお参り。 JR柏原駅から歩く。柏原の成菩提院は、お寺では少ないらしい、節分の行事があるが、中山道を少し西に行った所のお寺さんでも、節分をやっていると聞いて尋ねてみた。どのお寺か判らなかった。勝専寺、教誓寺 をお参り。 |
|
 柏原の西の入り口から、300m程入ると、北条鎌倉幕府の転覆
を企て、この地で殺された北畠具行(ともゆき)の墓がある。 柏原の西の入り口から、300m程入ると、北条鎌倉幕府の転覆
を企て、この地で殺された北畠具行(ともゆき)の墓がある。
北畠具行を預かったのが、かの有名な、バサラ大名佐々木道誉だ。また、この佐々木氏の菩提寺が、この奥の清滝寺である。この両所のお参りは、今回省略。
|
|
 長沢(ながそ)の集落へ。長沢地名は、中小河川が一気に流れ下る地の名前。不破の関より古い、小川(こかわ)の関もこの地の山裾にあった。 長沢(ながそ)の集落へ。長沢地名は、中小河川が一気に流れ下る地の名前。不破の関より古い、小川(こかわ)の関もこの地の山裾にあった。
|
|
 一色に入る手前に、お地蔵さんを集めた小屋があった。この辺りは地蔵畑と言う地名で、戦死者を葬った地で、地蔵石仏が沢山、野にあったとの事。これらを集めた物だろうと勝手に思う。 一色に入る手前に、お地蔵さんを集めた小屋があった。この辺りは地蔵畑と言う地名で、戦死者を葬った地で、地蔵石仏が沢山、野にあったとの事。これらを集めた物だろうと勝手に思う。
なお、地蔵畑と言う地名は、全国に在るようだ。
一色集落を抜けると、醒井(さめがい)。
|
|
 居醒の清水(いさめのしみず)。地蔵川の
水源の湧水箇所。富士山の規模には敵わないが、相当量の湧水量だ。伊吹山に住む大蛇退治にきた日本武尊が、高熱で倒れたときに、この泉で身体を癒したと伝わる。 居醒の清水(いさめのしみず)。地蔵川の
水源の湧水箇所。富士山の規模には敵わないが、相当量の湧水量だ。伊吹山に住む大蛇退治にきた日本武尊が、高熱で倒れたときに、この泉で身体を癒したと伝わる。
|
|
 日本武尊が出てくる所は、鉄に関係する場所が多い。伊吹、醒井、南宮大社みんな鉄絡みで、そこの住民も、外来の技術集団の人達だ。 日本武尊が出てくる所は、鉄に関係する場所が多い。伊吹、醒井、南宮大社みんな鉄絡みで、そこの住民も、外来の技術集団の人達だ。
|
|
 賀茂神社お参り。なお、日本武尊の像が賀茂神社鳥居の右に建っていた。 賀茂神社お参り。なお、日本武尊の像が賀茂神社鳥居の右に建っていた。
|
|
 地蔵堂お参り。昔、大干ばつのとき、伝教大師最澄が降雨を祈願して地蔵菩薩を
彫ったところ、大雨が3日間降りつづいたと言う。初めは水中に安置されていたので、尻冷し地蔵と呼ばれていた。地蔵堂は、江戸時代、大垣城主石川日向守が病気全快を感謝し建立したもの。
今はこの中。お地蔵さんは、見られなかった。 地蔵堂お参り。昔、大干ばつのとき、伝教大師最澄が降雨を祈願して地蔵菩薩を
彫ったところ、大雨が3日間降りつづいたと言う。初めは水中に安置されていたので、尻冷し地蔵と呼ばれていた。地蔵堂は、江戸時代、大垣城主石川日向守が病気全快を感謝し建立したもの。
今はこの中。お地蔵さんは、見られなかった。
|
|
 了徳寺お参り。境内に、御葉附銀杏(おはつきいちょう)あり。葉っぱに種が付いているそうだ。天然記念物。 了徳寺お参り。境内に、御葉附銀杏(おはつきいちょう)あり。葉っぱに種が付いているそうだ。天然記念物。
|
 中山道が地蔵川を渡る所の川の中に十王水の灯篭が建っていた。平安時代の十王堂跡との事。
十王堂は昔流行った物だそうだ。閻魔さんなど10大王をお祭りしている。 中山道が地蔵川を渡る所の川の中に十王水の灯篭が建っていた。平安時代の十王堂跡との事。
十王堂は昔流行った物だそうだ。閻魔さんなど10大王をお祭りしている。 |
|
  なお、100mほどの所に、泡子塚(あわこつか)がある。茶屋の娘が
、旅の途中の西行が残したお茶の泡を飲んだところ、男の子が出来た。西行が帰りに寄り、この話を聞いて、もし我が子ならば泡に戻れと言って、「水上は清き流れの醒井に浮き世の垢をすすぎやみん」と詠むと泡と消えたそうだ。西行は実に我が子なりと、この所に石塔を建てたという。今もこの辺の小字名を児醒井という。 なお、100mほどの所に、泡子塚(あわこつか)がある。茶屋の娘が
、旅の途中の西行が残したお茶の泡を飲んだところ、男の子が出来た。西行が帰りに寄り、この話を聞いて、もし我が子ならば泡に戻れと言って、「水上は清き流れの醒井に浮き世の垢をすすぎやみん」と詠むと泡と消えたそうだ。西行は実に我が子なりと、この所に石塔を建てたという。今もこの辺の小字名を児醒井という。
あまり意味が判らないが、この話がずっと続いてきた事は、なにか意味があると思う。
|
|
醒井駅の西北の丹生川が天野川と合流する辺りは、壬申の乱の激戦地だった。やじり等が出るそうだ。現地へ行ってみたが、説明文、碑などは何もなかった。
|
|
 川南(かわなみ)の名神高速の向こう側にある神社、八坂神社へ、九重塔を尋ねたが、見つからなかった。神社を間違えているかな? 要再調査。 川南(かわなみ)の名神高速の向こう側にある神社、八坂神社へ、九重塔を尋ねたが、見つからなかった。神社を間違えているかな? 要再調査。
この辺りの鎌倉古道は、はっきりしないようだ。インターネットで、”鎌倉街道”で検索すると、1000件以上ある。100件の内容を見てみると、滋賀県以西は、大阪豊中が1件のみであった。本当に跡形もないのか、感心が低いかは、判りません。
|

米原インターチェンジの際に、久礼の一里塚跡があった。
謡曲「東国下」に、余り知られていない、醒井、番場、磨針(すりばり)、小野の地名が出てくる。
「船橋」に醒井が出てくる。
「いさむ心はなけれども、その名ばかりは武佐の宿。まだ通路も浅茅生の小野の宿より見渡せば、斧を研ぎし磨針や。番場と音の聞こえしはこの山松の夕あらし、旅寝の夢も醒が井の自ら結ぶ草枕」
|
 番場の東の口に立派な石碑。 番場の東の口に立派な石碑。 |
  以前素通りした蓮華寺お参り。勅使門が戸が閉まり構えて建っていたので、入れないのかと思った。 以前素通りした蓮華寺お参り。勅使門が戸が閉まり構えて建っていたので、入れないのかと思った。
|
 勅使門には、菊の紋が附いていた。歴代天皇の帰依厚く、紋の使用に、OKが出たと、その謂われ
が立て看板に説明してあった。聖徳太子が創建との説明もあり。 勅使門には、菊の紋が附いていた。歴代天皇の帰依厚く、紋の使用に、OKが出たと、その謂われ
が立て看板に説明してあった。聖徳太子が創建との説明もあり。 |
|
  鎌倉幕府六波羅探題の北条仲時以下430名余の墓。足利尊氏に追われ、ここで、自害。是を悼んだ歌碑が幾つか建っていた。 鎌倉幕府六波羅探題の北条仲時以下430名余の墓。足利尊氏に追われ、ここで、自害。是を悼んだ歌碑が幾つか建っていた。
|
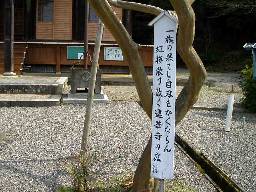  一族の果てし自刃もかくならん 紅梅散り敷く蓮華寺の庭 作者不明 一族の果てし自刃もかくならん 紅梅散り敷く蓮華寺の庭 作者不明
自刃せし遠祖の眠る蓮華寺 散り敷く紅葉流る如 朽竹
|
|
  松風の音聞くときは古への聖の如く我は寂しむ 斉藤茂吉 松風の音聞くときは古への聖の如く我は寂しむ 斉藤茂吉
|
  蓮華寺開基の鎌刃城主土肥三郎元頼の墓と伝える宝篋印塔もあった。また、番場の忠太郎墓、親子縁結びの忠太郎地蔵さんが建っていた。 蓮華寺開基の鎌刃城主土肥三郎元頼の墓と伝える宝篋印塔もあった。また、番場の忠太郎墓、親子縁結びの忠太郎地蔵さんが建っていた。 |
 |
|
 番場の街道沿いに、少し不釣り合いに感じる、鎌刃城趾の大きな表示があった。往復3、4時間掛かりそうだ。 番場の街道沿いに、少し不釣り合いに感じる、鎌刃城趾の大きな表示があった。往復3、4時間掛かりそうだ。
|
  名神の直上を通る中山道を通り、小さな峠を越え(帰り調べたら小摺針峠とありました)、三叉路で右に曲がる。摺針の集落の外れに、摺針峠あり。例の明治天皇お休み所の大きな碑がある望湖堂あり。中へは入らなかった
。 名神の直上を通る中山道を通り、小さな峠を越え(帰り調べたら小摺針峠とありました)、三叉路で右に曲がる。摺針の集落の外れに、摺針峠あり。例の明治天皇お休み所の大きな碑がある望湖堂あり。中へは入らなかった
。 |
|
  峠を下りると国道8号線。昔の旅姿3態の像のある彦根市の、お出向かい塔。 峠を下りると国道8号線。昔の旅姿3態の像のある彦根市の、お出向かい塔。
直ぐ旧道に戻り、鳥居本の町を行く。茅葺きの家が残っていた。
「右 彦根道の道標」の通り、右に折れ、彦根へ向かう。
|
|
 途中、佐和山トンネルを通る。歩行者専用の小さなトンネルがあった。四国遍路で、やはり歩行者専用のトンネルが1つあり、感心した事を思い出した。この分だと日本国には、案外歩行者用トンネルがありそうだ。 途中、佐和山トンネルを通る。歩行者専用の小さなトンネルがあった。四国遍路で、やはり歩行者専用のトンネルが1つあり、感心した事を思い出した。この分だと日本国には、案外歩行者用トンネルがありそうだ。
|
|
本日の歩いた概要図

|
| |
| 以 上 TOPへ戻る
|