|
5 関ヶ原 野上 垂井 南宮神社 赤坂 美江寺 河渡 岐阜
30km 1996/09/04
中山道へ
|
| 関ヶ原から歩き始める。
 道の開削で北側がえぐられている桃配山。徳川家康が本陣を置いた所だ。また、壬申の乱の時の吉野
軍の本陣でもあったようだ。 道の開削で北側がえぐられている桃配山。徳川家康が本陣を置いた所だ。また、壬申の乱の時の吉野
軍の本陣でもあったようだ。
桃配山の由来説明板があった。吉野軍の大将、大海人皇子が陣を張った時、桃を献上したところ、これがあまく甘かったので、全軍の兵士に配った。士気がいやがうえにも高まり、大勝した。それから桃配山と言うようになった
とのこと。
|
 関ヶ原町野上の里。謡曲「班女」の古里。野上の宿の女、花子が旅の途中の吉田少将と契るが、少将の去った後、忘れられず、形見に交わした扇を持って訪ね歩いた末、京の糺すの森で再会する物語である。
関ヶ原町野上の里。謡曲「班女」の古里。野上の宿の女、花子が旅の途中の吉田少将と契るが、少将の去った後、忘れられず、形見に交わした扇を持って訪ね歩いた末、京の糺すの森で再会する物語である。
班女の名は、漢の宮女、班女が帝の寵愛を失ったのを、「秋の扇」に例えたことに由来する。班女の観音堂があった。
|
 昔の姿を残している垂井の一里塚、国の指定史跡となっている。 昔の姿を残している垂井の一里塚、国の指定史跡となっている。 |
 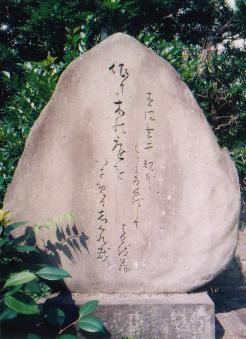 本龍寺をお参り。お寺の一部は脇本陣門を移設したとのこと。また、芭蕉ゆかりの時雨庵あり。 本龍寺をお参り。お寺の一部は脇本陣門を移設したとのこと。また、芭蕉ゆかりの時雨庵あり。
「作り木の庭をいさめるしぐれ哉」の句碑。
|
  南宮大社の大鳥居。南宮大社をお参り。鍛冶屋、金属屋の神様である。
大和朝廷の征伐する所は、大抵、鉄を産するところのようだ。何気ない神話のようであるが、よく見てみると、いろいろ読めるものがあるようです。 南宮大社の大鳥居。南宮大社をお参り。鍛冶屋、金属屋の神様である。
大和朝廷の征伐する所は、大抵、鉄を産するところのようだ。何気ない神話のようであるが、よく見てみると、いろいろ読めるものがあるようです。 |
 垂井の泉。大ケヤキの根本から、湧き出ていて、枯れることがない。平安時代から歌に詠まれている
とのこと。 垂井の泉。大ケヤキの根本から、湧き出ていて、枯れることがない。平安時代から歌に詠まれている
とのこと。 |
 室町幕府も少しぐらつき始めの頃、応仁の乱の始まる20年位前に足利の一族の反乱があった時、負けた足利持氏の遺児、春王丸、安王丸は捕らえられ、京へ送られる途中、ここで殺された。辞世の歌が残っている。お墓をお参り。 室町幕府も少しぐらつき始めの頃、応仁の乱の始まる20年位前に足利の一族の反乱があった時、負けた足利持氏の遺児、春王丸、安王丸は捕らえられ、京へ送られる途中、ここで殺された。辞世の歌が残っている。お墓をお参り。
春王丸 13歳 夏草や青野が原に咲くはなの身の行衛こそ聞がまほしけれ
安王丸 11歳 身の行衛定めなければ旅の空命も今日に限ると思えば
|
 垂井の追分。東海道に出る美濃路との分岐点。 垂井の追分。東海道に出る美濃路との分岐点。
青墓の里。頼朝、義経らの父、源義朝は平治の乱で破れ、子の義平、朝長とともに、ここ青墓まで逃れ来た。ここで、重傷の朝長が死に、義朝は、この後、知多野間にて殺された。朝長の墓が山の中に残っている。
謡曲「朝長」がある。
また、熊坂長範の物見の松がある。謡曲「熊坂」の長範である。朝長、熊坂とも、今回は省略した。
|
 小篠竹
(こざさだけ)の塚あり。「青墓にむかし照手姫という遊女ありこの墓なりとぞ 照手姫は藤沢にも出せりその頃両人ありし候や詳ならず」の説明があった。 小篠竹
(こざさだけ)の塚あり。「青墓にむかし照手姫という遊女ありこの墓なりとぞ 照手姫は藤沢にも出せりその頃両人ありし候や詳ならず」の説明があった。
しかし、慈円の歌あり。「一夜見し人の情にたちかえる心に残る青墓の里」
|
 赤坂宿の赤坂港跡。昔は船の交通網があった所。 赤坂宿の赤坂港跡。昔は船の交通網があった所。 |
 呂久(ろく)は今の揖斐川左岸にあるが、江戸時代は右岸だった。
揖斐川の今と違っていた。明治時代に今の流れに改修したとの説明があった。 呂久(ろく)は今の揖斐川左岸にあるが、江戸時代は右岸だった。
揖斐川の今と違っていた。明治時代に今の流れに改修したとの説明があった。 |
  美江寺宿は、本陣跡はあったが、宿場の雰囲気は何もない。 美江寺宿は、本陣跡はあったが、宿場の雰囲気は何もない。
河渡宿も何もなし。
|
| |
|
以 上 TOPに戻る
|