|
36 島原 上賀茂神社 曲水宴 社家の家並み 京都 8km 2010/04/11
|
| 上賀茂神社の曲水宴に、歌の仲間、3人で出かけた。7時、東岡崎駅出発。新幹線を使う。
JR丹波口駅を降りて島原へ。 |
 9:20 島原歌舞練場跡。 9:20 島原歌舞練場跡。
花街(かがい 歌舞音曲の遊宴の場 遊郭ではないという)には、必ず歌舞練場があった。今の祇園、上7軒町なども同じ。
|
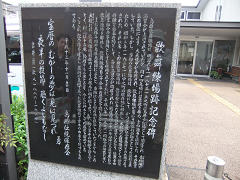 島原歌舞練場の説明と吉井勇の歌。 島原歌舞練場の説明と吉井勇の歌。
宝暦のむかしの夢は見は見つれ夜半の投節(なげぶし)聴くよしもなし 勇 |
 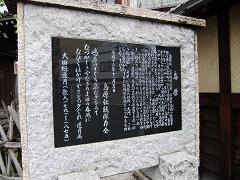 島原の入り口 大門 島原の入り口 大門
島原のでぐちのやなぎをみて 蓮月 江戸時代後期の尼僧・歌人・陶芸家。 |
 置屋(おきや)の 輪違屋(わちがいや) 非公開。 置屋(おきや)の 輪違屋(わちがいや) 非公開。
置屋 太夫や芸妓を置いて、揚屋へ派遣する店。
大門、置屋の輪違屋、揚屋の角屋 島原の面影を残す物は、この3つのみ。 |
  10:00 置屋(あげや) 角屋(すみや)。 10:00 置屋(あげや) 角屋(すみや)。
公開されている。 置屋 今の料亭に当たるもの 台所があり、宴会の出来る大広間、茶室付きの庭があることが条件という。 |
 長州藩志士 久坂玄瑞(くさかげんずい)の密議の角屋 の碑。 長州藩志士 久坂玄瑞(くさかげんずい)の密議の角屋 の碑。
久坂玄瑞は、高杉晋作・吉田稔麿・入江九一とともに松下村塾の四天王といわれた。 |
   角屋の玄関。 角屋の玄関。
玄関脇の昔の冷蔵庫。 |
 新撰組、芹沢鴨が残したという、刀傷。 新撰組、芹沢鴨が残したという、刀傷。 |
 帳場。 帳場。
すべて、付けだったという。 |
  階下の松の間。 階下の松の間。
臥龍の松のあり、茶室3つある、庭がある。
|
 長さのある、軒。 長さのある、軒。 |
   庭。 庭。 |
 東鴻臚館(ひがしこうろかん)址 角屋の北。 東鴻臚館(ひがしこうろかん)址 角屋の北。
平安時代、京の中央を南北に朱雀大路が貫き、その七条以北の東西にふたつの鴻臚館(外国の使者の接待の場)が設けられていた。 白梅や墨芳こしき鴻臚館 与謝蕪村 |
 島原西門 島原西門島原八景の内、西口の菜花 花の色はいひこそ知らね咲きみちて山寺遠く匂ふ春風 富士谷 世章 富士谷 世章 江戸時代の国学者。 |
 10:40 10:40
島原住吉神社 西門の際にあり。 JR丹波口駅〜JR二条駅 電車に乗る。 |
 11:10 JR二条駅。 11:10 JR二条駅。
バスで北賀茂神社へ。降りて昼食。
|
  12:10 上賀茂神社。 12:10 上賀茂神社。
正式名称 賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ)。 一の鳥居。 奈良の小川。
|
  曲水宴会場の渉溪園。 曲水宴会場の渉溪園。
賀茂ぜんざいの無料接待所。 |

13:00 曲水宴。 本殿拝礼の後、平安時代の服装で、会場へ。
|
  歌人 米田律子氏。 歌人 米田律子氏。
冷泉為弘氏 |
 
歌人 永田和宏氏。 河野裕子氏。 |
 奉行 京都市長の挨拶。 奉行 京都市長の挨拶。 |
 奉仕役 去年の 葵祭の斎王代が行う。千万紀子さんといい、茶道裏千家の娘さんという。 奉仕役 去年の 葵祭の斎王代が行う。千万紀子さんといい、茶道裏千家の娘さんという。
今年は、写真撮影に良い場所を見付けた。 |
   羽觴(うしょう)を流し。 羽觴(うしょう)を流し。
觴 盃のこと。 |
 歌人は歌を短冊に。 歌人は歌を短冊に。 |
  盃を乗せた乗せた羽觴を受け、酒を飲む。 盃を乗せた乗せた羽觴を受け、酒を飲む。 |
  被講(ひこう 冷泉家の人々による朗詠)。 被講(ひこう 冷泉家の人々による朗詠)。 |
 |
| 曲水宴が終わった後、歌人の歌の印刷物を貰い、野点のお茶をいただく。
東京の婦人と会う。昨日、諏訪大社に行き、今日は、こことのこと。歌を詠んでるらしい。我らより上手らしい。 |
  細殿と立砂(たてずな)。 細殿と立砂(たてずな)。
細殿前の円錐状の二つの砂の山は御神体である神山を模したもの。鬼門にまく清めの砂の起源という。 楼門。 |
 結婚式を終えた新郎新婦。 結婚式を終えた新郎新婦。 |

14:30 社家の家々。 家がなくなり、空き地となっている一角があった。 |
| 15:30 京都駅。
上賀茂神社からバスに乗った。50分。新幹線で帰る。12千歩。 |
|
以 上 TOPへ戻る |