

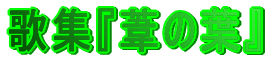
(引用・解釈)2003年2月 引用者
この歌集『葦の葉』には驚き、感心させられる。若い時も、年を重ねても、その純粋さ
一徹さは、変わるところがない。そして、時々の出来事、世界のことも、日本のことも、
顔を出す。そして、それが、自身の生活ときっちり結びついており、それがよくわかる言
葉で言い表されている。たとえば、こうだ。
車よりさし出す白手袋の手を握る病みあとのきみはや声嗄れて
県議会選挙 (昭和五十四年)
選挙を闘うその人は、誰であったのだろう。そして、敦夫氏は、その友人に手を差し伸
べ、体のことを心配している。
思想も、生活も、同じところで描くことができている。
このわれに未だ寄る来る一人なりきその彼もこの春転任されき(昭和三十六年)
数々の差別を受ける身なれば、「時世に敏感」なる人々は、去っていく。(不当な人事
によって引き離されるというべきだ。)しかし、正直なるが故に、私に接する彼も、今年
は転任という。このように「人事」は行われもした。
伝馬町に女主人の小さき店ありき月々買ひぬ『マルクス主義』を(昭和五十四年)
思想は失わない。いや、失うものかという気概を感じる。
早く亡ききみを思へば悲し悔し飯島宗一は名古屋大学学長となりぬ(昭和五十四年)
これは、どう読むのだろう。飯島氏があの名古屋大学の学長という。それよりも、はる
かにすぐれ、思想もあった彼は、病のためか早く去ってしまった。その彼のために、悔し
いと思う杉敦夫がいる。
授業は楽しいと言ふこの男も校長になれぬ老いぼれ教員 (昭和三十三年)
これは、現実の問題だ。どんなにがんばっても、自分では正しい道と思っても、世間も
同僚も「評価」してはくれぬ。「子どもとともに」「授業は楽しい」と言ってみても、何
か「負け犬」のように自分が思えてしまう。
そんな感覚が支配する三河の教育現場。それは、今も変わらない。しかし、組合を作っ
た我々は、はるかに自信を持って前進しつつあるし、堂々と「一教師としての道」を歩み
つつある。
しかし、当時は。愛知の運動に、本当の組合運動がなかったことが、どれほど多くの教
員の希望を奪ってきたことか。「支配するもの」だけでなく、「支配される側」の弱点も
時代を作る要因となっている。
以上は、まず私が気になった歌だ。
以下、重なりも気にせず、年代ごとに歌を抜粋していこう。
「短歌集」から
(昭和十年)
腹立たしく 物言はぬ 吾れにあらがはず 妻は傍に来て 眠りたり
何に腹を立てていたのだろう。昭和10年とは1935年。中国大陸では日本の侵略で戦争が
激しくなっていた。
(昭和十二年)
額に入り 鴨居にありし 吾が妻の 教員免許状も いつかしまひぬ
教員同士で結婚し、教育への夢も語ったであろう夫婦。しかし、「共働き」は当時はさ
らに難しかったのだろう。いきおい妻は子育てと家事に。そして、いつしか夫や家族のた
めに教職から去ることも。それは、今も。「鴨居に教員免許状を」かざったことが「誇り」
でもあった妻の教員としての人生は、過去のものに。
(昭和20年) 三河地震
三河地震のことであろう。1945年(昭和20年)1月13日(土)午前3時38分、
この地域をおそった地震は甚大な被害を及ぼしたが、戦争中でもあり、その状況は伏せられた。
戦争と地震、この2大災難に人々は打ちのめされたであろう。
様々な体験が記録され、伝えられているが、それは人々の実感がそうさせたのであって、
政府の記録はほとんどないのが実態だろう。
それを、郷土歴家であった杉敦夫氏は、短歌に記録した。
食ひ違ひし畦に驚き立つ間にも南西より地鳴りとどろく
アララギは如何になりしや知らぬまま
歌送りつづけぬ三河地震の歌など
地図の上にしるしつつゆく断層線
三ヶ根山をめぐり居るらし
枯れ草の中に瀬音のひびきつつ
隆起地帯は白く涸れたり
仮小屋の屋根葺く藁屑散る村を
圧死せし汝を祈りつつゆく
雪散らふ谷辿りゆく土赤き断層線を仰ぎ見ながら
敵迎へ戦ふ時を云ひたりき忽ち圧死す海辺の村に
小隆起土竜の如く土もたげここにとどまる麦畑の中
雪の散る夕日に立てり突堤を崩して断層は海に入りたり
煤黒き大梁折れて垂れ下がる下に乏しく食らふ吾がうからら
(昭和20年) 敗戦(終戦)
肩寄せて女教師らは泣き出しぬ吾れはただただ打ち疲れゐて
なにに泣くというのだろう。張りつめた気持ちがぷつんと切れて。「国が負けた」から。
「国体護持」「国体護持」と叫びつつ兵事係は走り去りたり
敗戦の日、多くの人はただ泣いたであろう。亡くなりし人を思いつ、そして、この
つらい戦争の終わりを受け止めつつ。しかし、狂信者(時代を自らの頭で考えようとし
ないもの)はいる。この「狂信」は、この男だけのものではない、昨日までの私も
そうだったのだ。
(昭和二十二年)
この谷に 永遠に帰らぬ 君らのため めぐれる丘に 白き碑
戦争が終わり、少しゆったりと郷土を巡れば、還らぬ教え子・知人たち。墓だけが立っているが、
この戦争は破壊と死と、悲しみだけをもたらしたのだ。
(昭和二十三年)
農地改革 遂に理解せず 死にゆきし 父のむくろよ あはれ小さし
資本論 二度売りて 三度買ひぬ かくのごときが 吾れの一生か
思想を生きるとは、何と難しいことだろう。まがりなりにも、自らは「節を屈せず」生きてきた。しかし、
この本を手放した時のこと。それも二度。今度は、本当にこの本を自らのものすることはできるのだろ
うかと。
(昭和二十七年)
明治天皇 御製など いつまで説いているのだ 校長よ
ああ青ざめて 一人が倒れた
(昭和二十八年)
先生が なんと言っても 保安隊に 入るに決めたと 言ひ切りし彼
子どもは、教師の生き様を見てはくれない。戦争のつらさを教えたのは、君らではなかったのか。
その君らが再び復活すつつある軍隊に入ろうというのか。
(昭和三十三年)
授業は 楽しいと言ふ この男も 校長になれぬ 老いぼれ教員
「授業は楽しい。」二心なく言う我と彼。しかし、その彼も私も校長にはなれぬ。ひがんでいるのではない。
教師の道に確信を持ってはいる。しかし、彼も、私も、いまだに一教員。
缶詰に されて勤務評定 書いて来たらしい 校長の 少し青い顔を見る
評定せし 校長と されて吾らと こだはっているやうな
いないやうな 朝の集会
(昭和三十四年)
退職を 吾れに勧むる 老教育長 抽出を しきりに探し 何を出すのか
(昭和三十五年)
涙あふれ 退職挨拶する 山本さん
共に勧奨されし 吾れのしらじらといる
ストーブを 囲みて話す 吾等老教員 一人づつ
ドアの中へ 呼び込まれゆく
教員三十三年 歌作り二十八年 遂に遂に 無力にして 精根尽きぬ
抑え切れぬ 怒りの侭に 笑顔作る 生徒の前の 哀しき習性
教師とは、何と正直ではない仕事。退職を決意した私。それは本意ではないのだ。そして、私に
退職を勧めたこの体制。怒り、悲しみ、そして苦しみ。この思いを語る我ではなくて、とりつくろう我が
いる。
この新しき 語一つ 明日教へむと 蒲団より
首のばして メモする
潔き 退職を ひそかに 決めいしが 三池争議斡旋に
怒り 心変わりぬ
(昭和三十六年)
このわれに 未だ寄る来る 一人なりき その彼も この春転任されき
席向ふ 女教師に 誤読一つ 示すも一夜 迷ひたる後
(昭和三十七年)
事ごとに 叫びあぐるを もてあます 今年一年 限りの教師
(昭和四十年)
職引かば 楽しからむと 思ひしが 何か曖昧なる 気持ちになりぬ
単純なる 吾れには つひにつかみえぬ 深き心の 翳とぞ思ひき
校長に ならねば駄目だ 退職金が 百万円違ふと 幾人かに話しぬ
アメリカを 追ひ出すために 少年は 水田の中に 打たれ死にたり
ベトナム戦争
痛ましく 吾れの見て立つ 墳の石すれすれに
ブルドーザーの 刃往返す
「開発」という名のもと、いかに多くの歴史的遺跡が壊されていっただろう。今、私の見つめる
前で、また一つ。
労働終へ 化粧つつましき 少女らに 吾れは楽しく 古事記神話を説く
これは楽しい時間であった。勉強しようと集まった若き少女らに、「古事記」を語る。それは、
教員としての時間ではなく、自らの好きな学問を語る夕べであった。
自転車置場に ためらふごとく 立つ汝を 先程より見つつ 職員室に居る
生徒の日記 その母に 読み聞かせつつ 吾れは乱れて 涙を落す
教室の 腰掛並べ 仮眠する 再就職の われ憐れなり
三河地震の 断層たどり この峠 越えき疲れ知らざりし 戦争末期
人去りし 本堂に残る 君が棺 遅れ来りし 吾れの近づく
早川三雄急死
老妻の いづこよりか 帰りし音のして 吾が枕べに 夕刊を置く
血色よき 童顔の 小さき老人を 夏山茂樹と 聞きて驚く
山出でて 来りし道は 河原なり ここにあふれし 一揆勢思ふ
若きらに まじる老二人 暁に さめて少し話す アララギのこと
いつのことだったか、歌集『葦の葉』をみせていただいた時のこと。その歌の、あまりに生活感が
にじみでて、印象深かったこと。そして、私も「こんな歌を作ってみたい」と思った時のこと。
上記の歌は、私が勝手に書き出して、勝手に「感想」を書きたしたものです。ご容赦ください。
※ また、短歌の元は上記のようにはなっていませんが、詠みやすいように私の方で書き直しました。
これも、ご容赦ください。
この本は『歌集 葦の葉』杉敦夫(杉浦敦太郎) (昭和58年8月1日)に出版されました。
現代教育現場短歌集
他の方々からも短歌をいただきました。掲載します。
※ 2000年以降の教育現場は、更に忙しく、問題をはらんでいます。そこで、詠まれる短歌からは、深刻な現代日本の断面が垣間見えるようです。
教師と子どもたち
このような「標題」が適当なのか、わかりませんが、提供いただいた短歌を私なりに実感に即して、感想のようなものを書かせていただきました。
引き出しに鋭きペンを封じ込め闇にとびだし帰らぬ少年
作者 :大辻倫生(おおつじ のりお)
私は、この作者とは面識はないのです。杉浦敦太郎氏の短歌を詠んだときもそうでした。だから、私が思ったままを書き加えたのです。
この短歌の「鋭き」と「闇」が、妙にとげとげしく響きます。きっと、教室の雰囲気も、そんな「厳しいもの」があったのでしょう。教師とは、何事かが起きたときよりも、その後にこそいろいろ考えるものです。後悔と、反省と。
繊細で礼儀正しき女教師がやめざるを得ぬ高校の秋
良い教師ほど早く辞めていく。そんな言葉を聞きます。また、そんな辞めていった教師たちの顔が浮かぶのです。では、今もやっている私は。複雑な感情が心に。こんないい教師が辞めなくてはならない学校現場。未来は明るくないぞ、と叫ぶ辞めない教師がいる。
清らかな部分わかちもつ友たちも人事異動で散り散りになる
これに似た短歌を以前載せました。上記にありますが、杉浦敦太郎氏の短歌集からです。
このわれに未だ寄る来る一人なりきその彼もこの春転任されき(昭和三十六年)
似た歌です。そして、何十年も時を隔てて、同じ現実があるのです。志がある教仲間がいる。その教師たちが仲間となることを恐れるのか。職場の管理のために、心を許す教員仲間がバラバラにされていく。それは、教員の活力を失わせ、教え会う力を減退させていく。
声荒げなければ動かぬ君たちは鴉の雛か小評論家
これは、教師の陥りやすい精神状態。子どもらをこのように言ってしまう時、教師としての交代のはじまりだと思っていた私がいる。しかし、時として、このように言ってしまうのだ。子どもらよ。それは、私に原因があるのだろうか、君たちにか。こんな言葉を使う教師も、傷ついている。
君たちは過ぎてゆく風歩けない樹樹に向かってもう次の風
これも、むなしい歌ですね。教師が、このように書くのはなぜでしょう。「教えるとは、共に希望を語ること、学ぶとは、審理を胸に刻むこと」とは、何と素晴らしい言葉か。しかし、そうではない職場があり、醒めた目の私がいる。
集団の中に居るときの孤立感沈む心が荷物となりゆく
私も、以前書いたことがある。教師とは何とすばらしい職業であることか。しかし、教員がたくさんいるところは、なぜか苦手だ。そして、その雰囲気の悪いこと。なぜなのだ。
この集団は、子どもらの集団、教師の集団。その中で、何と孤独なのだ。それは、なぜなのか。
新任となりて数年君もまた大声をあぐるひととなりたり
この歌は悲しい。教師として力を着けていくというのは、こんなことであったか。技術は、身に付いていくだろう。しかし、子どもらに初めて接した時の感覚を失ってほしくはない。「真っ直ぐに並ぶと、気持ちいいよね。」なんて、言わないでほしい。それは、教師の気持ちがいいのであって、子どもの気持ちではないはず。そんなことが、分からなくなっていく教師の現実。
子どもたちに声を張り上げることにさえ、疑問を持った初めの頃。それが、今ではどうだろう。「叱るのはうまくなった」。でも、子どもらの心からも遠くなったのではないか。
それに気がつくか。いや、気がつかないのだ。部活に熱中する教師がいる。子どもを叱咤する教師がいる。
現場の教師は、いろいろな困難を抱えて日々こどもらと接しています。そして、教師としての人生を生きています。自分に問う、「これでいいのか」と。しかし、容易に答が見つかる訳ではないようです。
そんな教師の心を、いろいろな方法で語ろうではありませんか。
勿論、このように「歌」でもいいですね。
