1石山秋月(いしやまのしゅうげつ) 石山寺 2勢多(瀬田)夕照(せたのせきしょう) 瀬田の唐橋 3粟津晴嵐(あわづ のせいらん) 粟津原 4矢橋帰帆(やばせのきはん) 矢橋 5三井晩鐘(みいのばんしょう) 三井寺(園城寺) 6唐崎夜雨(からさきのやう) 唐崎神社 7堅田落雁(かたたのらくがん) 浮御堂 8比良暮雪(ひらのぼせつ) 比良山系
|
a 第15日目 2009/10/18 (日) 経路 −桜井市初瀬−長谷寺(鉄道)−奈良−9番・興福寺南円堂−興福寺阿修羅像展−奈良(鉄道)−宇治−10番・三室戸寺−宇治泊− 歩き距離 17.3千歩 11.2km 地図上距離 60km 出発 7時 到着 15時 晴れ すれ違ったお遍路さん 4人 宿屋 第一ホテル 泊まりのお遍路 0人
|
 7:30 初瀬の町並み。 7:30 初瀬の町並み。奈良泊まりを予定したが、すべて断られた。阿修羅展があるようですが、人が集まっているようだ。今日は、日曜日でした。 泊まりは、宇治に。 |
 7:40
近鉄長谷寺駅。 7:40
近鉄長谷寺駅。近鉄長谷寺〜近鉄奈良駅 電車使用。 |
 9:10 興福寺境内。 9:10 興福寺境内。 |
 9:20 第九番 法相宗 興福寺南円堂(こうふくじなんえんどう) 9:20 第九番 法相宗 興福寺南円堂(こうふくじなんえんどう)如意輪観世音菩薩 お参り。 |
  興福寺五重塔。 興福寺五重塔。興福寺南大門の発掘調査中。 |
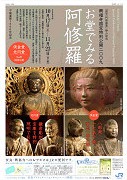 「お堂で見る阿修羅展」を見る。 「お堂で見る阿修羅展」を見る。興福寺 北円堂 仮金堂で公開。 並んで待って、拝見した。 阿修羅立像(八部衆のうち) 裏側をのぞき込んで見てきた。
|
 北円堂 弥勒如来坐像 世親菩薩立像 無着菩薩立像 四天王像(四像) |

仮金堂 釈迦如来ほか三尊像 四天王像(四像) 八部衆・十大弟子像
|
 11:00 猿沢池。 11:00 猿沢池。 |
  11:20
JR奈良駅。 11:20
JR奈良駅。作り替え工事中。 JR奈良駅〜JR宇治駅 電車使用。 |
 12:40
宇治川 宇治橋。 12:40
宇治川 宇治橋。岩間寺に電話したが、平日は、路線バスのみ、長距離歩かねばならない。バスの時間は知らないとの冷たい返事だった。 |
|
上醍醐寺と岩間寺について教えて貰おうと、参道で、婦人4人組の巡礼に声をかけた。 昨日、バスで、岩間寺へ行ってきた。上醍醐は、醍醐寺の境内にある、観音さんも拝めるとのこと。 ついでに、用済みといって、JR石山駅から岩間寺のバス時間表を貰った。 大変、助かりました。 先ほど、岩間寺に電話したが、平日は、路線バスのみ、長距離歩かねばならない。バスの時間は知らないとの冷たい返事だった。それで、声をかけたのだ。 |
  13:00
第十番 本山修験宗 明星山三室戸寺(みょうじょうさんみむろとじ) 13:00
第十番 本山修験宗 明星山三室戸寺(みょうじょうさんみむろとじ)千手観世音菩薩 お参り。 |
  本堂。 本堂。花の咲いていない時期でした。 |
|
宇治に戻り、平等院に行こうとしたが、人が多く、結局、入らずに戻った。 15:00 駅前に泊まる。 |
|
|

 7:40
JR宇治駅。
7:40
JR宇治駅。 9:00
第十一番 真言宗 深雪山上醍醐寺(みゆきやまかみだいごじ)
9:00
第十一番 真言宗 深雪山上醍醐寺(みゆきやまかみだいごじ) 上醍醐寺の観世音菩薩は、仮住まいをしていた。
上醍醐寺の観世音菩薩は、仮住まいをしていた。
 真如三昧耶(しんにょさんまや)堂。
真如三昧耶(しんにょさんまや)堂。

 9:30
金堂。
9:30
金堂。
 11:30
東海自然歩道になっている、山道を登る。
11:30
東海自然歩道になっている、山道を登る。
 12:10
第十二番 真言宗 岩間山正法寺(いわまさんしょうほうじ) 岩間寺
12:10
第十二番 真言宗 岩間山正法寺(いわまさんしょうほうじ) 岩間寺
 本堂。
本堂。

 銀杏の木。
銀杏の木。 12:40
芭蕉池と句碑。
12:40
芭蕉池と句碑。 14:10
岩間寺から石山寺まで歩く。
14:10
岩間寺から石山寺まで歩く。 第十三番 真言宗 石光山石山寺(せっこうざんいしやまでら)
第十三番 真言宗 石光山石山寺(せっこうざんいしやまでら)
 本堂。
本堂。
 蓮如堂。
蓮如堂。
 御影堂。
御影堂。 15:20
瀬田の唐橋。
15:20
瀬田の唐橋。 7:50
滋賀青年会館。
7:50
滋賀青年会館。
 瀬田川の琵琶湖方面
と下流。
瀬田川の琵琶湖方面
と下流。 8:20
粟津の晴嵐(せいらん)。
8:20
粟津の晴嵐(せいらん)。
 粟津の晴嵐碑付近の瀬田川。
粟津の晴嵐碑付近の瀬田川。 8:50
膳所(ぜぜ)公園。
8:50
膳所(ぜぜ)公園。
 9:00
京阪膳所本町駅。
9:00
京阪膳所本町駅。 9:30
義仲寺(ぎちゅうじ)。ここ大津は、木曾義仲が死んだ所で、その墓所。
9:30
義仲寺(ぎちゅうじ)。ここ大津は、木曾義仲が死んだ所で、その墓所。

 朝日堂(本堂)。
朝日堂(本堂)。 翁堂。奥の茅葺きの建物。
翁堂。奥の茅葺きの建物。

 木曾義仲の墓。
木曾義仲の墓。
 行春をあふミの人とおしみける 芭蕉桃青(とうせい 芭蕉の別の名)
行春をあふミの人とおしみける 芭蕉桃青(とうせい 芭蕉の別の名)

 10:10
ロシア皇太子遭難の地の碑。
10:10
ロシア皇太子遭難の地の碑。
 10:20
長等(ながら)神社 三尾(みお)神社 お参り。
10:20
長等(ながら)神社 三尾(みお)神社 お参り。
 10:50
第十四番 天台寺門宗 長等山三井寺(ながらさんみいでら) 園城寺(おんじょうじ)
10:50
第十四番 天台寺門宗 長等山三井寺(ながらさんみいでら) 園城寺(おんじょうじ)


 金堂。
金堂。

 11:20
小関越え(こぜきごえ)。
11:20
小関越え(こぜきごえ)。
 京都側は、歩く道が残っている。
京都側は、歩く道が残っている。 12:00
JR湖西線長等山トンネル、東海道線逢坂山トンネルの京都側。
12:00
JR湖西線長等山トンネル、東海道線逢坂山トンネルの京都側。
 三井寺観音
道の道標。
三井寺観音
道の道標。
 13:20 渋谷川田(しぶたにかわた)道の表示ある道。
13:20 渋谷川田(しぶたにかわた)道の表示ある道。
 13:30
番外 天台宗 華頂山元慶寺(かちょうざんげんけいじ)
13:30
番外 天台宗 華頂山元慶寺(かちょうざんげんけいじ)

 大石道(おおいしみち)の表示ある交差点。
大石道(おおいしみち)の表示ある交差点。 鳥戸野
(とりべの)陵の碑。
鳥戸野
(とりべの)陵の碑。 15:00 泉涌寺への道から、観音寺への道。赤い橋あり。
15:00 泉涌寺への道から、観音寺への道。赤い橋あり。
 第十五番 真言宗 新那智山観音寺(しんなちさんかんのんじ) 今熊野観音寺
第十五番 真言宗 新那智山観音寺(しんなちさんかんのんじ) 今熊野観音寺 時間が無くなり、大慌て。東大路通りを北上。ようやく清水寺。
時間が無くなり、大慌て。東大路通りを北上。ようやく清水寺。
 16:00
第十六番 北法相宗 音羽山清水寺(おとわさんきよみずでら)
16:00
第十六番 北法相宗 音羽山清水寺(おとわさんきよみずでら)


 8:00
第十七番 真言宗 補陀洛山六波羅蜜寺(ふだらくさんろくはらみつじ)
8:00
第十七番 真言宗 補陀洛山六波羅蜜寺(ふだらくさんろくはらみつじ)
 鴨川 松原橋。室町時代の五条橋。
鴨川 松原橋。室町時代の五条橋。
 8:30
寺町京極と新京極。
8:30
寺町京極と新京極。
 東北寺誠心院
(せいしんいん) 真言宗。
東北寺誠心院
(せいしんいん) 真言宗。 五輪塔の和泉式部墓 お参り。
五輪塔の和泉式部墓 お参り。 8:40 浄土宗
誓願寺(せいがんじ)。
8:40 浄土宗
誓願寺(せいがんじ)。 信長の本能寺 法華宗。
信長の本能寺 法華宗。 京都市役所。
京都市役所。
 9:00
第十九番 天台宗 霊麀山革堂行願寺(れいゆうさんこうどうぎょうがんじ)
9:00
第十九番 天台宗 霊麀山革堂行願寺(れいゆうさんこうどうぎょうがんじ)

 高倉通りの足袋屋、分銅屋。
高倉通りの足袋屋、分銅屋。 9:40
第十八番 天台宗 紫雲山頂法寺六角堂(しうんざんちょうほうじろっかくどう)
9:40
第十八番 天台宗 紫雲山頂法寺六角堂(しうんざんちょうほうじろっかくどう)
 六角形の本堂。
六角形の本堂。
 11:10
東寺 教王護国寺(きょうおうごこくじ)。
11:10
東寺 教王護国寺(きょうおうごこくじ)。

 東寺 食堂(じきどう) お参り。朱印を受ける。
東寺 食堂(じきどう) お参り。朱印を受ける。

 12:20
西本願寺。
12:20
西本願寺。
 13:20
東本願寺。
13:20
東本願寺。 9:30
今日は休日。
9:30
今日は休日。 鴨川と三条大橋。
鴨川と三条大橋。
 10:00
平安神宮と神宮道。
10:00
平安神宮と神宮道。 10:10
白河院庭園と法勝寺跡。
10:10
白河院庭園と法勝寺跡。 永観堂総門。
永観堂総門。
 10:30
哲学の道。
10:30
哲学の道。 10:50
浄土宗 善気山法然院 萬無教寺(ぜんきさんほうねんいんばんぶきょうじ)
10:50
浄土宗 善気山法然院 萬無教寺(ぜんきさんほうねんいんばんぶきょうじ)

 山門。
山門。
 本堂。
本堂。
 11:10
阿育王塔。
11:10
阿育王塔。
 比翼塚 潤一郎の字らしい。
比翼塚 潤一郎の字らしい。 川田順の墓。
川田順の墓。 11:30
臨済宗 銀閣寺 東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)。
11:30
臨済宗 銀閣寺 東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)。

 本堂。
本堂。
 東求堂(とうぐどう)。
東求堂(とうぐどう)。

 観音殿(銀閣)。
観音殿(銀閣)。

 お茶の井。
お茶の井。 展望所から。
展望所から。 13:10
臨済宗 金閣寺 鹿苑寺(ろくおんじ)
13:10
臨済宗 金閣寺 鹿苑寺(ろくおんじ)

 金閣。
金閣。
 方丈。
方丈。

 安民澤(あんみんたく)。
安民澤(あんみんたく)。
 茶室 夕佳亭(せっかてい)。
茶室 夕佳亭(せっかてい)。
 8:00
阪急四条駅。 阪急東向日(ひだしむこう)駅。
8:00
阪急四条駅。 阪急東向日(ひだしむこう)駅。 9:40
善峯寺東門。
9:40
善峯寺東門。
 第二十番 天台宗 西山善峯寺(にしやまよしみねでら)
第二十番 天台宗 西山善峯寺(にしやまよしみねでら)

 本堂から山門を見る。
本堂から山門を見る。 10:10
三鈷寺(さんこじ)
10:10
三鈷寺(さんこじ) 10:30
善峯寺から1.6km。
10:30
善峯寺から1.6km。
 11:30
関西電力西京都変電所。
11:30
関西電力西京都変電所。 15:20
第二十一番 天台宗 菩提山穴太寺(ぼだいさんあのおでら)
15:20
第二十一番 天台宗 菩提山穴太寺(ぼだいさんあのおでら)
 本堂。 多宝塔。
本堂。 多宝塔。 円山応挙生誕の地
円山応挙生誕の地
 8:40
JR亀岡駅。
8:40
JR亀岡駅。
 9:50 JR山崎駅。
9:50 JR山崎駅。

 離宮八幡宮 お参り。
離宮八幡宮 お参り。 10:00
山崎あたりの複々線の東海道本線。
10:00
山崎あたりの複々線の東海道本線。


 10:30
桜井駅跡。
10:30
桜井駅跡。
 楠公父子子別れの石像。台座に「滅私奉公」。
楠公父子子別れの石像。台座に「滅私奉公」。 芥川宿と芥川一里塚跡。
芥川宿と芥川一里塚跡。
 13:40 継体天皇陵 お参り。
13:40 継体天皇陵 お参り。 14:10 第二十二番 真言宗 補陀洛山総持寺(ふだらくさんそうじじ)
14:10 第二十二番 真言宗 補陀洛山総持寺(ふだらくさんそうじじ)


 14:40
阪急総持寺駅。
14:40
阪急総持寺駅。