三河教労機関紙2006年度連載
『日中・太平洋戦争と教育』第12回 2007年5月
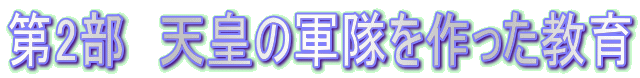
第2章 教育勅語 その2 『教育勅語」がもたらした”悲劇”』
前回の第9回では、「12の徳目の行き着く先」と題して、教育勅語の「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ…」といった12の徳目の行き着く先は、戦争になったら勇んで戦場におもむき、天皇のために命を投げ出して戦えということだ、と述べました。
今回は、教育勅語がもたらした“悲劇”と「小学校教師ニ賜ワリタル勅語」について書きます。
“絶対的な神”に、ひれ伏させるための儀式
第8回で、瀬戸内寂聴さんの自伝から、教育勅語が奉読される式の様子を紹介しました。「白い手袋をはめた(校長の)十本の指が講堂壇上の正面の檜(ひのき)の開き戸にかかった瞬間、私たちは長い最敬礼を強いられる。上気した顔を上げてみると、あけはなされた開き戸の、紫の幕のかげから、くもった鏡のように、にぶく光る御真影(ごしんえい)が見下ろしている。白い手袋の手が、桐の箱のふたをとり、にんじゅつの巻きもののようなものを、うやうやしくおしいただく。ふたたび、こんどこそ無限に長いように思われる最敬礼の号令がかかる。意味もわからない、お経のような教育勅語がえんえんとつづく間、上体をおりまげ、床をみつめていなければならない退屈と苦痛は、小学一年生や二年生の小さいからだと幼い神経には、たえがたい、ごうもんであった。」
|
最敬礼【説明】最敬礼は天皇陛下をはじめ奉り皇族、王公族に対して奉りて行なうもの…。最敬礼は先ず姿勢を正し、正面に注目し、状態を徐に前に傾けると共に手は自然に下げ、指尖(ゆびさき)が膝頭の辺に達するのを度(45度)としてとどめ、凡そ一息の後、徐に元の姿勢に復する。殊更に頸を屈したり、膝を折ったりしないようにする。文部省制定『昭和の国民礼法』昭和17年 |
『最モ尊重ニ』の重圧は校長、教員にも
教育勅語が発布された翌年の1891年に、文部大臣名で各道府県に次のような訓令が出されました。
「管内学校ヘ下賜セラレタル天皇陛下皇后陛下ノ御影並ニ教育ニ関シ下シタマイタル勅語ノ謄本ハ校内一定ノ場所ヲ撰ヒ最モ尊重ニ奉置セシムヘシ」
『教育勅語の研究』の著者岩本努氏は、「文面は簡単であるが、『最モ尊重ニ』の5文字は千釣の重みがあった。地震、火事、風水害、津波、火山噴火といった天地異変の際にも、御真影と勅語謄本は教員の命にかえても『奉安』しなければならなかった。『奉安・奉護』できなかった校長・教員・用務員への処罰の過酷さと、命を賭して守護した美談のキャンペーンが教育関係者をちぢみあがらせた。」と述べています。
“神”から下された教育勅語の重圧は、子どもだけでなく、校長や教員にも重くのしかかり、数々の“悲劇”を招いたのです。岩本氏は、前著に「教育勅語の事件簿」と題して、「主要なもの」60あまりの“事件”を記載しています。その中から紹介します。
殉 職
◆「御真影を守ろうとして最初の殉職者が出た」のは、1896年(明治29)の、三陸地方を襲った大津波で、岩手県下閉伊郡箱崎尋常高等小学校訓導兼校長栃内泰吉53歳である。
◆ 1902年(明治35) 栃木県上都賀郡足尾町神子内尋常小学校 豪雨で神子内川が氾濫した。学校内に住んでいた教員は、学校が危機にひんしたので妻と子を安全な民家に非難させ、人々の制止を押し切って再び学校に戻った。多分勅語を取り出すためだったと言われている。すでに完全に水に包囲されていたので、濁流に飛び込んでいった。
◆ 1915年(大正4) 石川県能美郡丸山尋常小学校杖出張所 午前1時に出火。代用教員壬生米吉は、同校に宿泊中の児童を救出し、勅語謄本を持ち出し、窓際に至って焼死した。
◆ 1923年(大正12) 関東大震災 数多くの教員が、御真影や教育勅語を守ろうとして殉職した。二葉尋常小学校では4名が殉職した。都が編纂した『大正震災美績』は、『嗚呼佐々木訓導』『山本校長と佐藤訓導の壮烈なる最期』などと、殉職した人々を讃えた。

「教育勅語の事件」で、“火災”と同じく多かったのが“盗難”でした。犯人探しをめぐって自殺者まで出ました。
◇ 1915年(大正4) 新潟県頚城郡上名立 「東方遙拝」 朝会では皇居に向かい最敬礼をする小学校 教育勅語等が紛失、捜査は難航したが、犯人として元次席訓導(教頭)竹内伝蔵(34)に嫌疑がかけられた。竹内は「憤慨満腔見よ我が血色を唯七度生まれても真の犯人と御所在をつきとめ之を奉安するの一事に犠牲たりし…」という遺書を残して首をつりました。
『小学校教師ニ賜ワリタル勅語』
教育勅語は、児童生徒に対するものでしたが、教員に対する勅語も別にありました。
第7回で取り上げた三浦綾子さんの『銃口』に、次のような場面が描かれています。
「柱時計が七時を知らせた、と、職員たちは一斉にその場に起立して、校長の方を見た。校長はみんなに背を向けて立った。校長のうしろには、日の丸の旗を入れた額が掲げてあった。教頭が大きい声で言った。『小学校教師ニ賜ワリタル勅語』職員たちは声を揃えて勅語を唱え始めた。『国民道徳ヲ振作シ以テ国運ノ隆昌ヲ致スハ其ノ淵源スル所実ニ小学校教育二在リ事ニ其ノ局ニ当ルモノ夙夜奮励努力セヨ…』一同がよどみなく明晰に唱和した。」
この風景を“過去のもの”として一笑に付すことはできません。三浦綾子さんの『銃口』は、「お上(政府)に忠実な教員」が再びこのような道を進むことを警告しています。