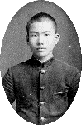
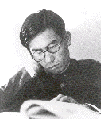
連載『日中・太平洋戦争と教育』第13回 第2部 天皇の軍隊を作った教育 2007年5月
第3章 軍事教育(1) 新美南吉と“軍事教練”
身体検査で岡崎師範学校“不合格”
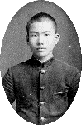 |
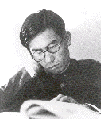 |
| 半田中時代 | 東京外語時代 |
『ごんぎつね』で知られる愛知県出身の童話作家、新美南吉は、教師になろうと愛知教育大学の前身である岡崎師範学校を受験しますが、不合格になりました。南吉は、東京の師範学校も受けますが、不合格となります。成績は優秀で、中学5年のときは92人中2位の成績でしたが、身体検査の成績が悪くて不合格になったと言われます。
南吉の体は「体重がなくて胸が小さく」、身体検査の結果は、小学6年が“丙(へい)”で、卒業する中学5年の時は“乙(おつ)”でした。
南吉は、東京に出て東京外語学校に学びます。そして、教員免許を取ろうとしましたが、免許を取れませんでした。その原因は、“軍事教練”の成績が悪かったからだと言われています。軍国主義の時代に教師になるには、兵士と同じように屈強な体が必要とされたのです。
南吉が師範学校を受験したのは、日本軍部が満州事変(1931年9月)を起こしたころでした。
軍隊の検閲を通って教員に
 |
| 軍事教練 |
南吉が不合格になった“師範学校”は、どんな学校だったのでしょうか。再び、三浦綾子さんの『銃口』から引用します。
「師範学校在学中の二年間は全寮制だったから、同じ市内にありながら竜太も家を離れて寮生活をしていた。師範学校の生活は五年間の中学校のそれとは、全くちがった雰囲気であった。全寮制であることも、上級生下級生のけじめがきびしいことも、学校というより軍隊に似ていた。
朝は鐘の音で一斉に飛び起きる。そしてあわただしく洗面、乾布摩擦、体操、掃除、朝食と、朝はとりわけ目まぐるしかった。つづいて登校。寮の門限は午後4時半、夕食は五時、夕食後は黙学の時間があって、消灯は九時半と決められていた。むろん僅かながら自由時間はあっても、芳子に会う時間などある筈もなかった。…寮は一部屋に四、五人、上級生下級生が組み合わされていた。この上級生の走り使いに下級生は追いまわされ、入浴の時も下級生は上級生の背中を流さねばならなかった。
その封建的なあり方に抵抗して、三年生のある生徒は学校をやめようと決意した。が、彼はやめなかった。師範生は、学費も被服費も貸与されていて、退学する者は、全額学費も被服費も返還しなければならなかったからだ。師範生のほとんどは秀才であったが、家の貧しい者が大方だった。何百円もの学資の返還など負担できる父兄は皆無といってなかった。…学校をやめようと思ったその生徒が、『一旦入学したら、やめる自由もこの学校にはないんだよ』と嘆いていたのを、竜太も聞いていた。しかしその生徒がやめたかった本当の理由は、配属将校がきびしい軍事教練の中で、常に言っていた言葉にあった。配属将校は、『君らは畏れ多くも天皇陛下の訓導になる身であるぞ』と、絶えず口うるさく言っていたのだ。…そしてこの三月、竜太は二年間の学びを終えた。終えるや否や、卒業生たちは勤務地に赴任する前に、旭川師団に入隊した。四月一日から八月三十一日までの入隊期間であった。その総仕上げの第一期検閲が終って、初めて教壇に立つことが許されたのだ。」
軍国教育を貫徹させるためには、児童生徒を指導する教員を、兵士と同じように軍隊的な「訓練」をする必要があったのです。
南吉の体は、それに耐えれるだけの強さを持っていませんでした。
虚弱な体ゆえに生み出された南吉童話
南吉が外語学校を卒業したのは、昭和11年3月(1936年)です。教員免許を取れなかった経過を、戯曲『新新美南吉物語』は、次のように描いています。
| 多蔵(父) | 「なんで、中学の先生の免許は取れんかったんですかのう。手紙には、軍事教練に出なかったので、それがいけなかったと書いてはあったんですがのう。」 |
| 伊藤照(恩師の妻) | 「その通りなんですよ、本人は、文学を志している自分の人生には、軍事教練など必要ないと思い、サボってばかりいた。だが、そのため教師の免許がおりないとは、全く意外であったと、私のところへ来た手紙には、そのように書いてありました。」 |
南吉は、「文学を志している自分には、軍事教練など必要ないと思い、サボってばかりいた」と手紙に書いていたというわけですが、実際はそればかりが理由ではなかったとわたしは感じます。貧弱な肉体しか持ち合わせていなかった南吉は、過酷な“軍事教練”に肉体的についていけなかったでしょう。ゆえに、意味や価値を見い出せなかったのではないでしょうか。
もし、南吉が人並な身体を持ち、身体検査が“甲(こう)”だったならば、成績優秀な南吉は、三浦綾子さんや瀬戸内寂聴さんのように、“軍国少年”になっていたのではないでしょうか。わたしには、南吉の心やさしい童話は、彼が虚弱な肉体を授かったがゆえに産み出されたように思えてなりません。