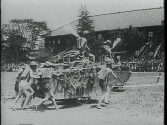
連載『日中・太平洋戦争と教育』第14回 第2部 天皇の軍隊を作った教育 2007年9月
第3章 軍事教育(2) 二人の教員
脳裏に焼きついた、対照的な二人の教員の生きざま
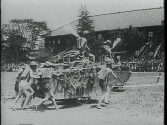 |
| 戦車まで繰り出す“戦争ごっこ” |
「軍事教育」という言葉で思い出すのは、20年以上前に見た映画に登場した、二人の教員の姿です。東京都教組が作ったその映画は、わたしの心に焼き付いています。
一人の教師は、当時の軍国主義教育にまい進し、木や紙で鉄砲や大砲、そして戦車まで作り、子どもたちにみごとな“戦争ごっこ”をさせて評判になりました。のちに校長になり、今(映画が作られた当時)は老人会の中心となって活躍しています。
もう一人の教師は、子どもたちに生活を見つめさせようと、「生活綴り方教育」に打ち込みますが、官憲にひっぱられて教壇を追放されます。しかし、子どもへの思いは断ち切れず、学校の前に文房具屋を開いて、子どもの近くで生活しています。
わたしの脳裏に、この二人の教員の対照的な生きざまが強く焼き付いています。
わたしは、この連載を書くなかで、この二人の教師と映画のことを紹介したいという思いを強くしました。そこで、夏休みに、記憶をたどってあるお宅を訪問しました。どっしりとした農家の構えのその家は、すぐに見つかりました。そのお宅の高校の教員をしていた息子さんが、平和に関するフィルムを何本か持ってみえて、わたしは何回かフィルムをお借りしたことがありました。その方に聞けば、映画のことがわかると思ったのです。家にはお母さんがみえて、連絡先を教えていただきました。今も高校の教員をしてみえるその方に電話で話すと、数日して映画のパンフが送られてきました。見たことのある、懐かしいパンフでした。
二人は、子どもが大好きで教員になったが
映画の題は、『子どもたちの昭和史 第二部 十五年戦争と教師たち』で、製作は1984年、今から23年前の作品でした。パンフには、次のように書かれています。
「戦争がだんだん拡大されていくなかで、子どもたちを教えていた小学校の教師たちは何をしていたのだろうか」「二人の教師が登場します。山形県の清野高童と、栃木県の川又圭です。二人とも子どもが大好きだったから教師になったといいます。」
 |
 |
| 山村で綴り方教育に打ち込む | 学校前に文房具店を開く |
「清野高童は、山形の山村で、子どもたちに本当のことを書く力をつけようと、新しいつづり方教育をします。」「清野高童は、子どもたちに真実を見つめる目を養ったというカドで特高に捕まります。取り調べがつづき、ついに供述書を書かされます。警察から釈放されたあとは、依頼退職をさせられて、教壇から去ります。」
「戦後は教職に復帰しますが、レッド・パージで再び教壇を去ることになります。」 「二度目の失業となった清野は、子どもたちと離れたくない一心から、小学校のそばで文房具店を開いて、今でも子どもたちの明るい声にとりかこまれています。」
 |
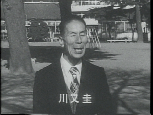 |
| 本格的な戦争ごっこは評判に | 今は公民館に勤める |
「川又圭は、夜もランプの灯の下で子どもたちに補習を行います。」「川又圭は、給与をそっくりそそぎこんで木や竹を使って飛行機、戦車、大砲、機関銃などを子どもたちと作りました。それらを使って校庭で、子どもたちに本格的な戦争ごっこをやらせます。戦争ごっこは、もう子どもの遊びではなく、戦争を体験させる教育になってしまったのです。子どもたちはおもしろくてそれに熱中し、ひとりでに兵隊の気持ちを行動を学んでいくわけです。子どもたちは、戦争ごっこを、本物の兵隊さんの慰問にいって見せたりして評判になりました。」「39年教職にあって校長を最後に退職した川又は、公民館につとめていて、老人歌舞伎を公民館などで演じています。」
子どもたちを死なせたつらさと、繰り返させない決意
そして、パンフは、次のように続けます。
「この二人の教師の生き方そのものは、戦争、戦後のなかで教えつづけ、教え子や自分も戦争にとられ、多くの教え子を死なせ、敗戦とともに民主主義を教えてきた全国の教師たちすべての生き方に重なっていくのです。国の方針にしたがって戦争を教えたものも、戦争に反対したものも、ともにいうことばは、子どもたちを死なせたつらさと、二度とそのようなことはくりかえしたくないという決意です。」
わたしはこの映画を見て、川又さんのような先輩が犯した“過ち”を繰り返してはいけないと強く思いました。それが、川又さんがこの映画に出演し自分をさらけ出した勇気に対する、わたしの回答だと思っています。
パンフの最後は、「教師は、教育の現場で、いま何をなすべきか?二人の姿からその問いかけが聞こえてきます」という言葉で結ばれています。
この映画のパンフには、「あまりにも似ている1930年代と今。軍拡、増税、そして教育全般の反動化…。」「いま、中曽根首相らによって『教育大臨調』の名のもとに、戦争への深い反省から出発した戦後の民主教育の“清算”が声高く叫ばれています。」と書かれていますが、20数年たった今、わたしたちは、さらに深刻な事態を迎えています。
機関紙特集に戻る 前のページ 次のページ