三河教労機関紙2006年度連載 『日中・太平洋戦争と教育』 第3回 2006年8月
![]()
![]()
7月末に、作家の吉村昭氏が亡くなりました。氏は、徹底した史実調査でリアリズムを追求し、骨太の文体で独自の作風を築いたといわれます。
代表作に「戦艦武蔵」「陸奥爆沈」などがあるように、太平洋戦争の知られざる事実に迫った作家でした。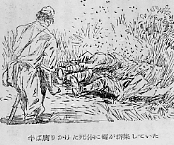
吉村氏の自選作品集第3巻に、「背中の勲章」という作品が収められています。 この作品は、太平洋戦争で米軍の捕虜第2号になった中村末吉氏の体験を取材して書かれたものです。中村氏は、米軍の捕虜収容所をあちこちまわされ、アメリカ西部のウィスコンシン州マッコイの収容所で、次のような光景を目にしました。
吉村昭自選作品集第3巻「背中の勲章」P105より
|
秋が深まったある日、中村は、亡霊の群れをみたような戦慄を感じた。 |
その夜半「顔をはげしく痙攣させて」明け方までに五人の者が死んだと書かれています。
南太平洋の小さな島ガダルカナル島を巡り、日米両軍は争奪戦をくりひろげました。
開戦から2年目の1942年8月から翌年の1月までの半年間です。
![]()
1998年に製作されたアメリカ映画で「シン・レッド・ライン」という作品があります。最前線で「死に直面した」兵士の死への恐怖がそのまま伝わってくるリアルな映画です。その戦場はガダルカナル島です。空に飛んでいるのは米軍の飛行機だけです。空も海も米軍に支配されていました。
ジャングルの日本軍陣地に踏み込むと、なすすべもなく祈る者や、銃も持たずに逃げ
惑う兵士がたくさんいます。日本兵は飢えていたのです。吉村氏の「背中の勲章」に描かれた亡霊の群れは、その姿です。ガ島からの撤退を指揮した今村均大将は、その回顧録に次のように書いています。
|
五ヶ月以前、大本営直轄部隊として、ガ島に進められた第十七軍の百武中将以下約3万の将兵中、敵兵火により斃れた者は約5千、餓死したものは約1万5千、約1万のみが、救出されたのだ。 (今村均『私記・一軍人六十年の哀歓』) |
そして今村大将は、責任を取って自決しようとした百武司令官に、次のように話して思いとどまらせたとのべています。 (同じく『私記』)
|
今度のガ島の敗戦は、戦いによったのではなく、飢餓の自滅だったのであります。この飢えはあなたが作ったものですか。そうではありますまい。日本人の横綱に、百日以上も食を与えず、草の根だけを口にさせ、毎日たらふく食っているかけだしの米人小角力に、土俵の外に押し出されるようにしたのは、全くわが軍部中央部の過誤によったものです。 |
兵士は、海も空も米軍に支配されたまっただ中に、一週間分の食料を背負って上陸しました。補給は満足にできません。食料が尽きたら、現地で何とかせよというわけです。全島が密林に覆われ、住民が少ないこの島では、食料を得ることはきわめて難しかった。空腹に耐えかね、野生の植物を食べて下痢を起こしたり、有毒植物に当たる場合も多かった。栄養失調で体力が衰えているため、赤痢やマラリア、その他の風土病への抵抗力もなくなり、次々と斃れていったといいます。
(藤原彰『餓死した英霊たち』)
かろうじて生き残った青年将校は、次のように書いています。(小尾靖男『陣中日誌』)
|
12月27日 今朝もまた数名が昇天する。ゴロゴロ転がっている屍体に蝿がぶんぶんたかっている。どうやら俺たちは人間の肉体の限界まできたらしい。生き残ったものは全員顔が土色で、頭の毛は赤子の産毛のように薄くぼやぼやになってきた。黒髪が、ウブ毛にいつ変わったのだろう。体内にはもうウブ毛しか生える力が… |